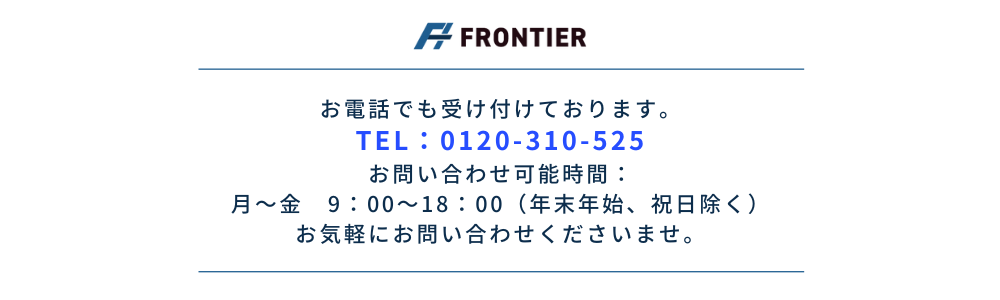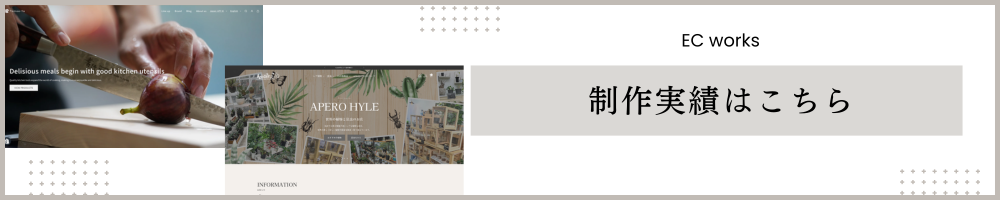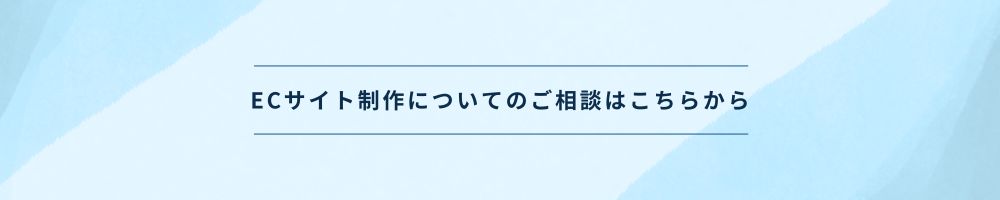【最新】越境ECとは?国内ECとの違いや始め方を解説
- ECサイト
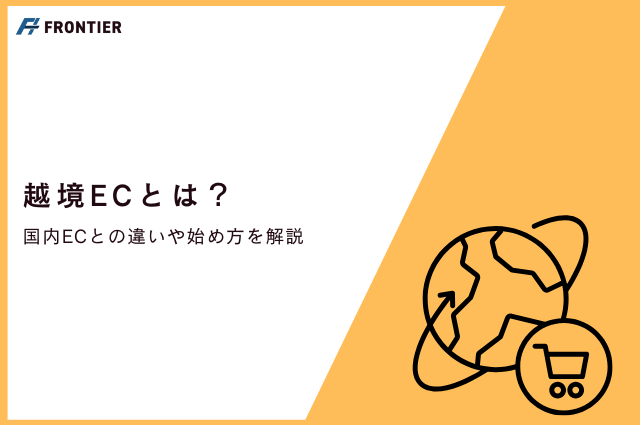
越境ECとは、文字通り“国境を越えて商品を届ける”ECのこと。
日本で運営しているネットショップを、海外のお客様にも開放して、注文を受けて届ける仕組みです。
「海外のお客様にも自分の商品を届けてみたい」
そんなふうに考える人が、ここ数年とても増えています。
かつて海外販売といえば、大手企業や専門業者が中心で、個人や中小企業にとってはハードルの高いものでした。
しかし今では、ECプラットフォームや翻訳ツール、国際配送サービスなどの環境が整い、誰でも越境ECにチャレンジしやすい時代になっています。
この記事では、越境ECの基本的な仕組みや国内ECとの違いをわかりやすく解説します。
「どんな準備が必要?」「何から始めたらいい?」という方も、この記事を読めばすすめてくださ越境ECの全体像がつかめるはずです。
海外展開を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
もくじ
越境ECとは?仕組みをわかりやすく解説

「越境EC」とは、インターネットを通じて海外のお客様に商品を販売することを意味します。
日本国内で運営しているオンラインショップを、海外のユーザーにも開放し、注文を受けて現地に届ける。そんな仕組みのことを指します。
たとえば、日本製のコスメをタイやベトナムで販売したり、アニメグッズをアメリカのファンに直送したり、和食器をヨーロッパの料理好きな人に届けたり。
実際にこうした例は、ここ数年でどんどん増えています。
以前は、海外販売といえば「輸出業者に頼む」「多言語サイトを自社で構築する」など、コストや手間が大きなハードルになっていました。
でも今は、Shopifyなどの越境対応ECカートや、多言語・多通貨・国際配送を支援する便利なツールが揃っていて、少人数のチームや個人事業でも始めやすくなっています。
すべての機能を自前で用意しなくても、ツールや外部サービスを活用することで越境ECは十分に始められます。
“まずやってみる”ことが成功の第一歩です。
ECサイトが“世界とつながる”ってどういうこと?
越境ECというと、「海外に送れるようにすればOK」と思われがちですが、実はもう少し奥が深いです。
本当に大切なのは、現地のお客様にとっても“買いやすい”環境をつくること。
たとえば、次のようなポイントがとても重要になります:
-
言語の壁をなくす:英語や中国語など、お客様の言語で商品ページを用意する
-
通貨を合わせる:円表記のままではなく、現地通貨で価格を表示する
-
配送・関税の不安を解消する:送料や到着までの目安、関税についての案内も忘れずに
こうした準備をしておくことで、お客様は安心して購入できますし、リピーターになってもらえる可能性も高まります。
つまり、越境ECは“日本のサイトに海外の人が来る”のではなく、その国の人に合わせて店を整えるという意識が大切です。
越境ECで成果を出すには、「海外に売れるようにする」だけでなく、
「現地のお客様にとってストレスなく買える環境」を整えることが成功の鍵です。
国内ECとの違いとは?
「国内ECとどう違うの?」というのは、初めての方が必ず気になるポイントだと思います。
ここでは、主な違いを3つにまとめてご紹介します。
1. ターゲットが違う
国内ECでは、当然ながら購入者は日本国内の方が中心です。
越境ECでは、アジア・欧米・中東など、国も文化も異なる人たちが相手になります。
そのぶん、好まれるデザイン・価格帯・商品説明のスタイルなども変わってくるため、「日本で売れているから海外でもウケる」とは限らない点に注意が必要です。
2. 決済や配送の仕組みが異なる
日本では当たり前の支払い方法や配送オプションも、海外では使われていないことがあります。
たとえば、クレジットカードよりPayPalやAlipayが主流の国もあれば、配送に追跡情報が必須という文化もあります。
3. 法規制や商習慣に対応する必要がある
商品によっては、輸出が禁止されている国や、成分の表示に特別なルールがある場合も。
特に、化粧品や健康食品、食品関連は注意が必要です。
販売前に「この国で売っても大丈夫か?」を調べておくことが大切です。
国によって規制が異なるため、販売前の確認は欠かせません。
なぜ今、越境ECが注目されているのか?
ここ数年で、越境ECという言葉を耳にする機会がぐっと増えてきました。
その背景には、日本の商品や文化への関心が高まっていること、そして誰でも挑戦しやすくなった環境の変化があります。
ここでは、特に注目されている理由を3つの視点でご紹介します。
1. 日本製品は「高品質」の代名詞
海外のお客様にとって、「Made in Japan」は今もなお信頼と安心のシンボルです。
丁寧なものづくり、安全な素材、繊細なデザイン——
こうした価値は、価格よりも“納得できる理由”として選ばれています。
特にコスメやキッチン用品、文房具や雑貨などは、品質を重視する人たちから長く支持されているジャンルです。
2. SNSで日本の魅力が世界中に届いている
InstagramやTikTok、YouTubeなどのSNSを通じて、日本のアイテムが“バズる”時代です。
たとえば:
-
抹茶味のお菓子が海外で話題に
-
アニメキャラのグッズが現地のファンに人気
-
パッケージのかわいさに惹かれて購入される化粧品 など
SNSでシェアされた投稿をきっかけに、「欲しい!」と思って越境ECで購入される流れがどんどん増えています。
3. “始めやすさ”が格段に進化している
以前は「海外向けに売る=ハードルが高い」と思われていましたが、いまは状況が大きく変わりました。
-
Shopifyなどのグローバル対応プラットフォーム
-
多言語・多通貨に対応したアプリや拡張機能
-
国際配送や関税処理を代行してくれるサービス など
こうしたインフラが整ったことで、小さなブランドや個人ショップでも越境ECに挑戦しやすくなったのです。
実際に始めた方からは、
「思ったよりカンタンだった」
「最初は不安だったけど、意外とスムーズに進んだ」
という声も多く聞かれます。
もちろん、運用には現地ニーズへの理解や改善の積み重ねが必要ですが、
まず一歩を踏み出すこと自体は、今の時代とてもやりやすくなっています。
「いつかやってみたい」ではなく、「まずは試してみよう」と思える環境が、すでに整っているのです。
越境ECで売れている商品ってどんなもの?
「うちの商品って、海外でも売れるんだろうか…?」
そんな不安が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
実際には、日本発の商品が“予想外の国”で注目されたり、「思いもよらないもの」が売れているケースも珍しくありません。
では、どんなジャンルの商品が、どんな国で人気を集めているのでしょうか?
ここでは、越境ECで反響の大きいカテゴリをいくつかご紹介します。
アニメ・キャラクターグッズ
日本のアニメや漫画は、言語の壁を越えて世界中で愛されています。
フィギュア、キーホルダー、文房具、Tシャツなど、関連グッズの需要は非常に高く、日本限定の商品や公式ライセンス品は特に人気です。
SNSで話題になったキャラクターやシリーズのグッズは、「自国では手に入らない」という理由で、プレミア感をもって受け取られることもあります。
和食器・包丁・キッチン用品
日本の食文化と“道具”へのこだわりは、海外の料理好きやプロの料理人たちにも強く響いています。
美しいデザインと実用性を兼ね備えた和食器や、切れ味・耐久性に優れた日本製の包丁などは、品質重視のマーケットで根強い支持を得ています。
「シンプルで美しい」「使うたびに気分が上がる」といった評価もよく見られます。
スキンケア・コスメ・健康食品
日本製のスキンケアや化粧品は、「成分がやさしくて信頼できる」「品質が安定している」という理由から、特にアジア圏で人気があります。
また、コスメだけでなく、サプリメントや自然素材を使った健康食品なども注目されており、“日常に取り入れやすく、安心して使えるもの”へのニーズは年々高まっています。
お菓子・抹茶・日本の食文化系商品
抹茶味のスナック、カラフルなパッケージのお菓子、駄菓子の詰め合わせなど、日本らしいユニークな食品は、「ギフト」や「体験」としても好まれます。
“かわいさ”や“遊び心”も価値として受け入れられるのが、海外マーケットの面白いところです。
「おもしろい!」「写真に撮りたくなる!」という視点も購買のきっかけになります。
越境ECを始めるには?準備とステップ
「やってみたいけど、何から始めればいいのかわからない」
越境ECに挑戦するうえで、最初のハードルはここかもしれません。
でも安心してください。
必要なステップをひとつずつクリアしていけば、初めての方でも無理なく始められます。
ここでは、実際の流れを3つのステップに分けてご紹介します。
1. プラットフォームを選ぶ
まずは、どの形で越境ECを行うかを決めることから始まります。
大きく分けて、次の2つの方法があります:
-
自社サイト型:ShopifyやBASEを使って、自分のオンラインショップを多言語・多通貨に対応させる
-
モール出店型:Amazon Global、eBay、Shopeeなど、すでに集客力のある海外ECモールに出店する
自社サイトはブランディングしやすく、自由度が高いのがメリット。
モール出店はスピード感を重視したい場合におすすめです。
どちらが向いているかは、「誰にどう届けたいか」によって変わってきます。
2. 多言語・多通貨・配送の体制を整える
越境ECでは、「翻訳」「支払い」「物流」の3つがとても重要です。
この3点がうまく整っていないと、購入直前で離脱されてしまう可能性が高まります。
✔ 翻訳:ページやコンテンツの重要度に応じて適切な対応を
海外のお客様に商品を届けるには、多言語対応が欠かせません。
しかし、すべてのページを完璧な翻訳にするのは、コストや時間の面から難しいのが現実です。
そこで大切なのが、ページの重要度に応じて翻訳の手法を使い分けることです。
-
一覧ページやブログの一部などは、自動翻訳でも対応可能
-
商品詳細ページ、カート周り、ブランド紹介など、購入や信頼に直結するページは、プロによる翻訳がおすすめ
-
特に「企業の想いや価値を伝えるコンテンツ」「広告やコピー」「キャンペーン告知」などは、ネイティブチェック付きの翻訳が理想的です
表現の微妙なニュアンスが伝わるかどうかは、購入意欲に大きな差を生むことがあります。
たとえば、肌に使うコスメや口に入れる食品の説明がぎこちないと、それだけで不安を感じてしまう方もいます。
だからこそ、「どこにコストをかけるべきか」を判断することが、越境ECでは重要になってきます。
すべてのページを翻訳するのではなく、購入や信頼に直結するページにしっかりコストをかけることが成功の鍵です。
通貨:価格の“わかりやすさ”が安心感につながる
日本円だけの表示では、海外のお客様にとって「結局いくらかかるのか」がわかりにくく、購入をためらわれる原因になります。
そのため、現地通貨での価格表示はとても重要です。
「見慣れた通貨で金額が表示されている」
ただそれだけで、価格のイメージがしやすくなり、不安がぐっと減ります。
-
アメリカ → 米ドル(USD)
-
ヨーロッパ → ユーロ(EUR)
-
東南アジア → 各国の現地通貨(THB、IDR、VNDなど)
また、決済方法もPayPalやAlipayなど、その国で一般的に使われている手段に対応しておくと安心感が増し、離脱率の低下につながります。
Shopifyの調査でも、多通貨・多決済に対応しているストアのほうが、コンバージョン率が高くなる傾向があると報告されています。
配送・関税:お届けまでの“見える化”が信頼につながる
越境ECにおいて、配送に対する不安は購入をためらう最大の要因のひとつです。
「いつ届くのか」「追跡できるのか」「追加で料金がかかるのか」
——このあたりの情報があいまいだと、せっかく買いたい気持ちがあっても、途中で離脱されることが少なくありません。
そこで、次のような工夫が効果的です:
-
配送方法と日数の目安をページ上に明記する(例:到着まで7〜10営業日など)
-
追跡番号の提供に対応することで、安心して待ってもらえる
-
関税や追加料金がかかる場合の説明を購入前に表示する(または関税込みの価格設計にする)
とくに関税は、「届いたときに思ったより高くついた」というマイナス体験につながりやすいため、事前に“わかるようにしておくこと”が信頼感に直結します。
「配送=届ける作業」ではなく、「安心して待ってもらう体験」まで設計することが、越境EC成功の鍵といえるでしょう。
3. 小さく始めて、データを見ながら育てていく
越境ECは、最初からすべてを完璧に準備する必要はありません。
むしろ、リスクを抑えるためにも「小さく始めて、少しずつ大きく育てていく」という進め方がおすすめです。
すべての国や言語に一気に対応しようとすると、準備やコストの負担が大きくなり、途中で止まってしまうことも。
実際、それが理由で手を引いてしまうケースも少なくありません。
そこで、以下のようなスモールスタートの進め方が現実的です:
-
-
まずは英語圏1カ国(アメリカ、オーストラリアなど)に絞って販売を始めてみる
-
商品は主力の数点に絞る(まずは反応を見たいラインナップだけ)
-
SNSや広告の発信も1つのチャネルに集中(Instagramだけ、Google広告だけなど)
-
こうして始めることで、次のような具体的なデータが手に入ります:
-
どの国からアクセスがあるのか
-
どの商品に反応が集まっているか
-
どんなページで離脱されているか など
このデータをもとに、
-
翻訳の見直し
-
表示価格の調整
-
よく売れる商品の強化
といった改善を少しずつ重ねていくことで、越境ECは“育って”いきます。
「小さく始める」ことは、失敗を減らすための方法であると同時に、長く続けるための戦略でもあります。
初めの一歩を軽やかに踏み出すことが、成功への近道です。
越境ECは完璧な準備からではなく、まず始めてみることが第一歩。
小さなトライを積み重ねて、改善していく姿勢が成功に繋がります。
越境ECを成功させるためのポイント
越境ECは、ただ「海外発送ができるようにする」だけでは成功しません。
大切なのは、現地のユーザーにとって“信頼できて、買いやすい”ストアであること。
ここでは、越境ECで成果を上げるために押さえておきたいポイントを3つに絞ってご紹介します。
1. 言語だけでなく、“文化”も伝える意識を
商品ページを翻訳することはもちろん大切ですが、それだけでは十分とはいえません。
大事なのは、現地のお客様がどう感じるか、どう伝わるかを意識することです。
たとえば、
-
写真に映る手の位置や背景の色
-
サイズ表記(cmだけでなくinchも)
-
商品名やキャッチコピーのトーン
こうした部分も、国や文化によって好まれるスタイルが大きく異なります。
「伝える」から「伝わる」へ。
越境ECでは、その感覚のアップデートが結果を大きく左右します。
2. SNSやレビューを活用して“信頼”を築く
海外のお客様にとって、初めて見るショップから買うのは勇気がいることです。
だからこそ、「誰かが買ってよかったと言っている」「このブランドは大丈夫そう」という安心材料がとても大切です。
そこで効果的なのが:
-
現地の言語でのレビュー掲載
-
SNSでのリアルなユーザー投稿の紹介(UGC)
-
インフルエンサーとのコラボや口コミ拡散
たとえ小さなレビューでも、“実際に購入した人の声”があるだけで信頼度は大きく変わります。
3. ユーザー体験(UX)を最後まで大切に
せっかく興味を持ってもらっても、「カートの使い方がわかりにくい」「配送情報が不明確」「問い合わせができない」といった理由で離脱されてしまうのはもったいないことです。
-
モバイルでも見やすいページ構成
-
送料や関税が明確にわかる説明
-
問い合わせ対応のスムーズさ(できれば現地時間にあわせて)
こうした細かなUX改善が、“買いやすさ”と“もう一度買いたい”の決め手になります。
越境ECを成功させるには、「売る」ことと同じくらい、「信頼される」「快適に買える」環境づくりが大切です。
お客様の目線に立ったひと工夫が、リピーターやファンづくりにつながっていきます。
まとめ|あなたの“好き”を、世界に届けよう
越境ECとは、いまや誰もが挑戦できる新しい販売の形です。
ツールやサービスが充実した今、個人や小さなチームでも、世界を相手に商品を届けられる時代になっています。
とはいえ、初めての越境ECには不安もつきもの。
言語、通貨、配送、文化の違い――どれも簡単ではありませんが、ひとつずつ整えていくことで、ちゃんとお客様に届く仕組みは作れます。
そして何より大切なのは、
あなたが「良い」と信じている商品やサービスに、自信を持つこと。
日本ならではの品質や感性、細やかな気づかいが、思いがけない国の誰かに「これが欲しかった」と届くことも珍しくありません。
まずは小さく、できるところから。
あなたの“好き”や“こだわり”を、越境ECという手段で世界へ届けてみませんか?